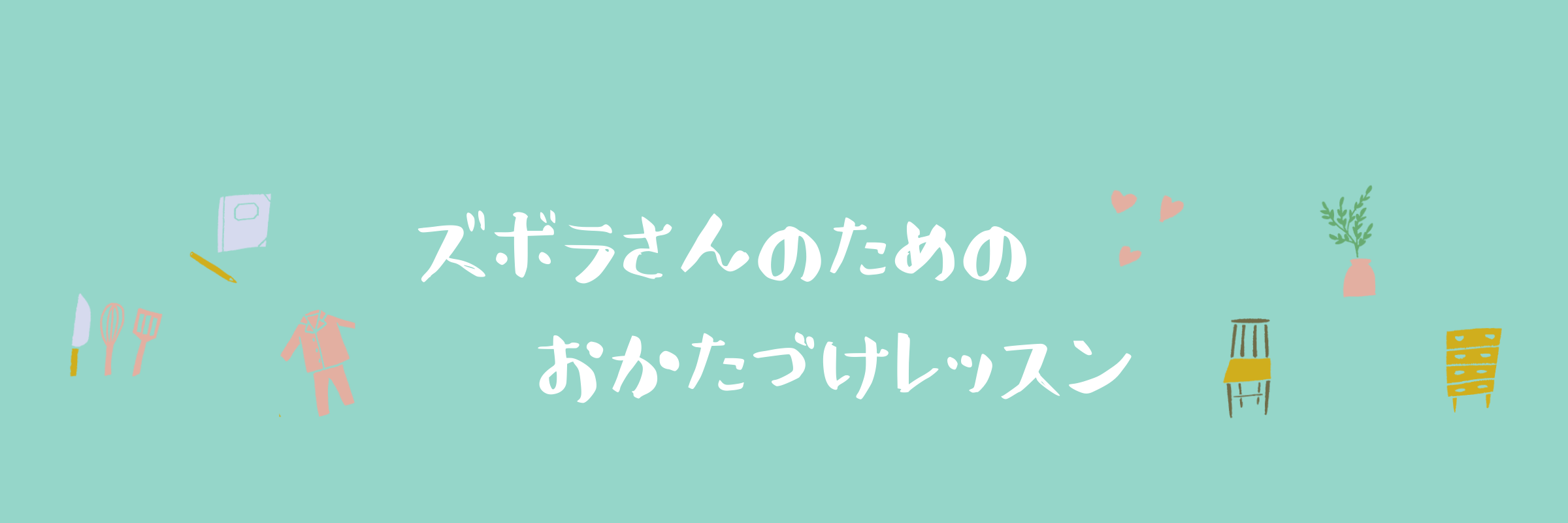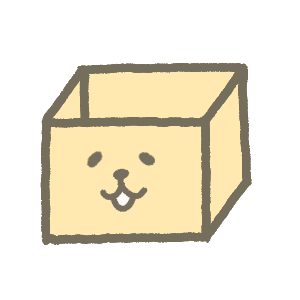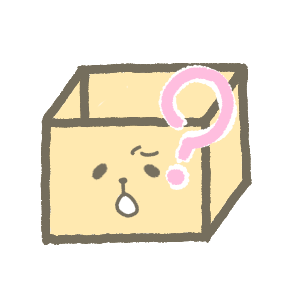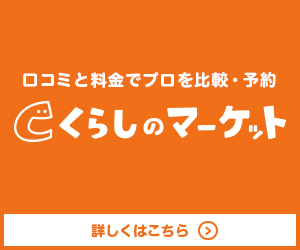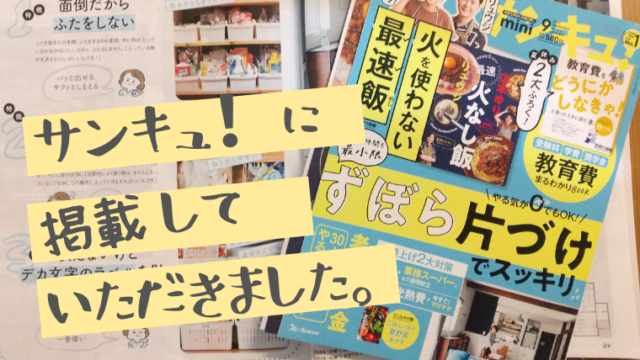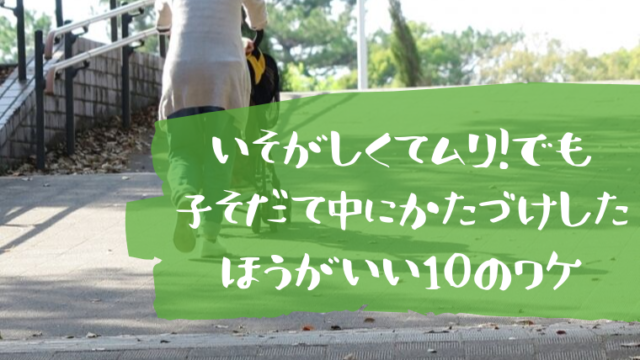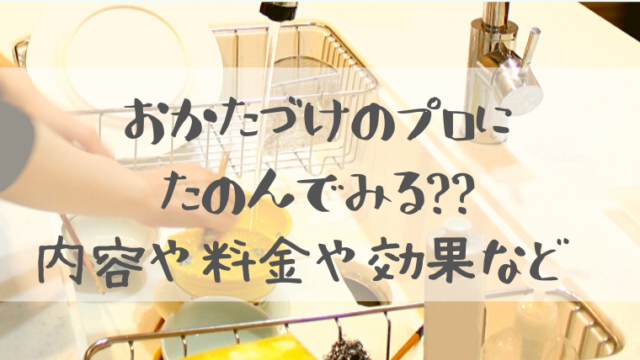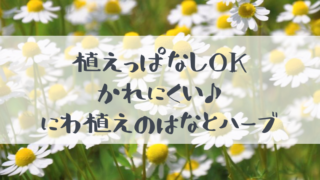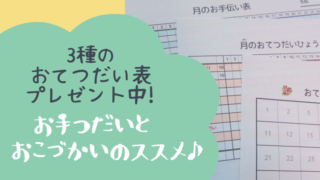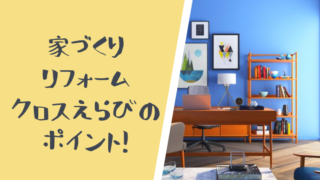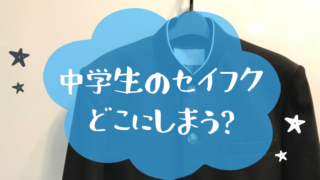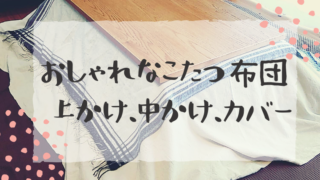「片付けられないのはなぜ?」
「どうしていつも部屋が散らかってしまうの?」
「どうして私は片付けができないの?」
とお悩みの方へ。
この記事では、片付けができない理由と、改善策についてお伝えしています。
片付けられない理由が分かると、サクッとお片付けができるようになる方も!
改善策を知って、できそうなところからトライしてみてくださいね。
片付けられないのはなぜ?できない10の理由と改善ポイント
さっそく、片付けられない10の理由についてみていきましょう。
- 物の量がキャパオーバー
- また使うからと、元に戻していない
- 取り出しにくい!だから戻すのも大変
- 片付ける習慣がない
- 片付いた超快適な空間を知らない
- とにかく忙しい!
- もともとの間取りが悪い、収納が少ない
- 買い物好き♡
- 子どもがいる
- 思い出の物、コレクションが多い
その理由と改善ポイントを順番にお伝えしますね!
物の量がキャパオーバー。管理できる量を超えている

お片付けができない理由の一つ目は、物の量。
持っている物の量が、自分の管理でき量を超えてしまっている事が原因です。
10個の物の管理と、100個の物の管理、どちらがラクか?といえば10個の物ですよね。
たくさんあればあるほど、管理するためのスペース、労力、時間、収納用品のお金が掛かります。
家賃も多く払っている可能性もあります。
逆に、10個のものだったら管理するスペースも、労力も、時間もかかりませんし、収納用品も必要ないかもしれません。
お片付けが苦手な人は、物の量を少なくすれば、高度な収納テクニックを駆使しなくても自然と片付くようになりますよ。
また使うから。ついつい面倒で…と、使った後戻していない。

お部屋が散らかってしまう原因2つ目は、物を定位置に戻していないこと。
「また使うから。」「ついつい面倒で…。」とそのままになってしまうことってありますよね。
もしかしたら、物を戻す定位置が面倒な場所になっているかもしれません。
例えば、コートの定位置が、2階のクローゼットだったらどうでしょう?
帰ってきて2階までしまいに行くことは、相当マメな方しかできません。
ソファーには、上着やかばんをつい置いてしまいがちですね。
では、どうしたら、ムリなく戻せるのでしょうか?
それは、行動動線上に収納の定位置を設けることです。
または、使う場所の近くに定位置を設けましょう。
- 玄関ホール
- 玄関からリビングの動線上
- 玄関から洗面所の動線上
- リビング など…
- 勉強する場所の横
- こまめに掃除したい場合はリビングに
定位置は、自分の生活の動きから考えるとムリなく片づけることができます。
物に人を合わせるのではなく、人の動きに物を合わせていきましょう。
必要に応じて、家具の配置を変えてみるのもおススメです。
取り出しにくい!だから戻すのも大変

お片付けできない理由の3つ目は、取り出しにくい収納であることです。
もし、あなたが戻すのが面倒な物があるとしたら、その物を取り出す際に、いくつのアクションが必要だったか思い出してみてください。
例えば…
- 扉を開けて
- その中の引き出しを開けて
- その中の箱をあけて取り出す
となると、目的の物を取り出すために3アクションあるということになります。
目的の物を取り出すのに3アクションあるということは、片付ける時も3アクション必要です。
そんな時は、アクション数を1つ減らしてみましょう!
アクション数を減らすコツは、フタやパッケージをとることです。

- フタがある場合はフタを切り取ってしまう(薬、絆創膏など)
- パッケージのある物はとってしまう(箱ティッシュ、電池など)
片付ける習慣がない
お片付けできない理由の4つ目は、使ったら戻すことが習慣になっていないことです。
習慣にするコツは、3週間続けること。
どんなことでも、3週間続けると習慣になるそうですよ。
最初は大変と感じるかもしれませんが、意識して続けていくと3週間後には片づけることが当たり前で、むしろ、元に戻さないことが気持ち悪くなるくらいに感じます。
習慣になってしまえば、頑張る必要はなくなります。
片付いた超快適な空間を知らない

お片付けできない理由の5つ目は、片付いた状態の快適な空間を知らないからかもしれません。
散らかっている状態が日常ですと、片付いた状態かどれだけ気持ちいいことなのか?ストレスがない状態なのか?もわかりません。
そんな方は、1度1部屋で良いので、「片づけきる」ということを体感してみてください。
一度味わうとその快適さが実感でき「元に戻りたくない!」という気持ちが湧いてきます。
そうなると、意識して物を増やさないようにしたり、自然と物を定位置に戻したりができるので不思議です。
自分一人ではできないという方は、お片付けのプロの力を借りてでも1度体感してみてくださいね。
とにかく忙しい!

お片付けできない理由の6つ目は、忙しいから、ということです。
私も独身時代は朝から晩まで仕事をしており、帰ってきたらとにかく「1分でも長く寝たい。」と思っていました。
でも、もしあなたが「お片付けができるようになりたい!」「部屋をきれいにしたい!」「片付けをして人生を変えたい!」と思うのであれば、1か月だけ優先順位を変えてみてください。
- 位 仕事する
- 位 遊ぶ
- 位 寝る
- 位 食べる
‥‥10位くらいに片付け&掃除
- 位 寝る(食べる)
- 位 食べる(寝る)
- 位 仕事や育児など
- 位 片付け
4位くらいに片づけを入れる
このように、優先順位の上位に片づけを入れて、空いた時間は片付けができたとすると1か月で片付いた部屋になり、さらには人生を変えることができるかもしれません!
そして、その頃には忙しいどころか、時間に余裕のある日々になっているはずです。
もともとの間取りが悪い、 収納が少ない

お片付けできない理由の7つ目は、もともとの間取りが悪かったり、収納が少ないということです。
お片付けができなくて困っている方のお家にお伺いすると、明らかに間取りが悪い!必要な場所に収納がない!という場合が。
間取りを変えることは簡単にできませんので、お家を自由設計で建てる人は片づけやすい間取りにすることが大切ですし、建売やマンションを買う方や賃貸の方も暮らしをイメージしながらお部屋を選びましょう。
という人は、こんな方法で改善してみましょう。
- 床から天井まで、収納を大胆に作る
- 部屋に入口が2か所ある場合は、1か所つぶして収納にする
- 引き違い戸は片側つぶして収納をおく
- 家具の配置を変える
買い物好き

お片付けできない理由の8つ目は、買い物好き、ということです。
手放す量より、家の中に入ってくる量が多いと片付きません。
捨てられないとか、片付けができない、という方は、消耗品以外の買い物はしないようにすれば物が増えることを防げます。
また、逆に買い物が好き!という方は、意識して同じ量を手放すようにすればお買い物を楽しみながら、物も増えない暮らしができますよ。
家に入ってくる物の量 > 手放す量 = 片付かない
家に入ってくる物の量 = 手放す量 = 現状維持
家に入ってくる物の量 < 手放す量 = 片付く
子どもがいる、子どもが多い

お片付けできない理由の9つ目は、子どもがいる(多い)ということです。
子どもがいれば、物の量が多くなりお片付けが大変になるのは当然のこと。
子どもがいる人は、2つの視点を取り入れてみましょう。
- 子どもに積極的にお手伝いしてもらい、お母さんの時間と心の余裕を作る
- 子ども1人1人の専用コーナー内で管理をしてもらう
お母さんのゆとりを作る、子どものお手伝い
子どもが多いということは、「手」がたくさんあること、でもあるわけです。
それぞれの役割分担を決めてお手伝いをしてもらえば、働き手がたくさんいるのでお母さんも助かるはず。
子どもにも積極的に家事に参加してもらいましょう。
我が家は子どもが3人おりますが、食器洗いとお風呂掃除は日常的に参加してもらっているので、大変助かっています。
子どもが小さなうちは、お手伝いをしたいといわれると、「自分が一人でやったほうが早いのに。」と正直面倒だったりもしますが、こどもが「やってみたい!」と言った時がチャンスです。
その時にお手伝いにチャレンジしてもらっておくと、数年後には立派な助っ人に。
お母さんの時間と心の余裕を作ってくださいね。
管理する力を育てる子どもの専用ロッカー

学校のロッカーのように、1人1人に専用の収納場所を割り当て、その中で自分の物の管理をしてもらうと、自分の物を自分で管理する力が身に付きます。
専用コーナーが溢れてきたら、見直すタイミング。
お子さんと一緒に「いるorいらない」の分ける練習をしてみてください。
想い出やコレクションが多い

お片付けできない理由の10こ目は、思い出やコレクションが多いからかもしれません。
まずは、思い出の品については、残す量の枠組みを決めて保存することをおススメします。
たとえば、自分の思い出の品は段ボール1つまで、などです。
箱の大きさは大小さまざまでよいですし決まりはないのですが、思い出は1人1箱で収まるくらいが理想的。
次にコレクションについてですが、好きなモノほど定位置を作って飾ったり、大事に管理してあげるとよいと思います。
自分が大好きな物、幸せを感じるものは大事にしてあげましょう!
まとめ
以上、片付けられないのはなぜ?できない10の理由と改善ポイントでした。
片付けられない理由が分かると、サクッとお片付けができるようになる方も!
できそうなところからトライしてみてくださいね。